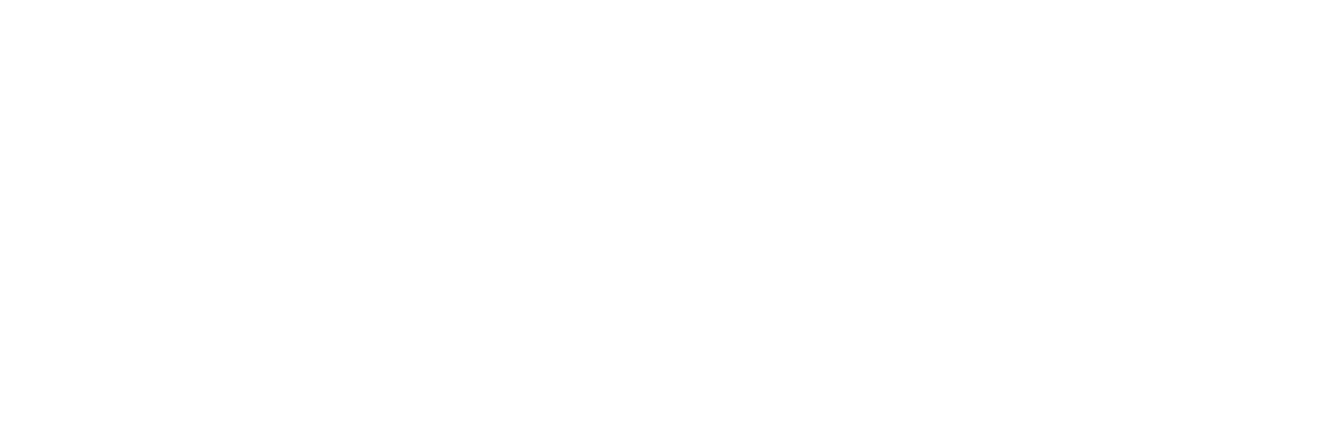比較文化学部 アジア文化専攻修了
新卒で入社した家電量販店では、コールセンターのオペレーターに従事。その後、働きやすい職場を求めて転職活動を行い、縁があって当社に入社。入社以来、重電課の事務を担当している。オフィスから離れた現場を後方支援する仕事の難しさを感じる中、先輩方がフォローしてくれる環境に感謝している。


入社後、まず習得に励んだのは社内で開発された経理システム。担当する支払関係業務などはこのシステムで管理するため、必ず必要となる知識の一つだ。しかし、前職ではシステムを使った業務の経験がなかったため戸惑いは大きく、当初は業務の流れとともに操作を覚えるのに必死だった。一通りの操作方法や手順をまとめたマニュアルを基に、限られた時間で正確かつスピーディに処理できるよう、先輩に教わりながらひたすら実践を重ねていく。心強かったのは、「間違えたら直せばいいから」という先輩の言葉。気持ちが楽になったのをよく覚えている。月末の各種支払い処理の際、金額の間違いや入力ミスなどもあったが、先輩にフォローしてもらいながら、仕事を覚えていくことができた。半年過ぎた頃には、先輩のフォローなしで任せてもらえるように。また、協力会社とのメールや電話のやり取りも増え、自信がついていった。
クレーンや車両関係の支払処理を任されるようになって以来、気になっていたことがあった。それは、月の最終日まで現場がある場合など、協力会社から届く請求書のタイミングにばらつきが生じ、結果として会計の締め作業が遅くなってしまうことが少なくなかったことだ。さらに、現場ごとに発生するすべての請求書を、それぞれの営業担当者に確認してもらう必要もあり、締切が遅くなればなるほど、担当者が仕事を終える時間も遅くなっていたのだ。そこで、請求書が全て揃ってから営業担当者に回示するのではなく随時、確認できるように課内で実践することになった。結果として、空き時間を有効に活用した確認ができるようになり、営業が早く退勤できるようになった。さらに、これまでより早く金額の相違に気づくこともできるようになり、精査の精度も高まっていった。営業担当者の後方支援をする立場として、作業の効率化に寄与できたのではないかと思う。


業務分担をしていた方が産休に入ったことで、今まで担っていた業務に変化。新たに、現場で使用する資材などの発注も担当することになった。それに伴い、今まで使用したことのない発注システムを、新たに覚えることにチャレンジした。さらに「3ヶ月を目途になんとかマスターしてほしい」というオーダーもあったので、システムに詳しい隣の課の先輩に教わりながら必死に習得に努めた。引き継ぎ後、初めての月末処理では、勘定科目の間違いなどのトラブルもあったが、周囲のサポートのお陰でなんとか乗り越えられた。場合によっては、協力会社への支払いが遅延する可能性もあったため、自分が携わる支払業務の重要性に改めて気づくことができた。次月以降は、自分なりにわかりやすく、勘定科目を一覧化し確認できるようにするなどの工夫を行いつつ、上長にダブルチェックを依頼。作業プロセスの見直しを行った結果、ミスが激減していった。そして3ヶ月が経った頃には、新たなシステムを問題なく活用できている自分がいた。周囲にはただただ感謝。


入社3年目の終わり頃から、お客様から約定通りお支払いしていただけているかといったキャッシュフローを毎月管理し、経理への報告を行う仕事を担当するように。重電課は展開しているプロジェクト数が多いため、営業担当者に各現場の状況をヒアリングしながら、過去に起こった請求の遅延などを理由ともに把握し、経理へ報告する資料を作成している。また、最近取り組んでいてやりがいを感じているのは、現場にてお客様に提出する安全書類の作成だ。現場に入る作業員は直前に決まることもよくあるため、書類作成の依頼が来てから提出までの期間が限られていることがある。そうした状況で、しっかりと書類を仕上げ、提出できた時に達成感を感じる。その度に、労いの言葉をいただくが、微力ながら社会インフラを構築していくプロジェクトの安全性担保に貢献し、現場の一員になれたと感じられることが嬉しい。
重電課ではさまざまな依頼が増えており、結果として遠方への長期間の出張を伴うプロジェクトもますます増えていくことになるだろう。当然、現場の担当者は慣れない土地で、必要以上にプレッシャーを感じることも予想される。そうした負担を可能な限り軽減し、プロジェクトのみに注力できるよう多岐にわたる後方支援を行うことが、結果として会社全体のパフォーマンスを高めていくと感じる。その一助となれるように、スキルとキャリアをアップさせていきたい。併せて、日々取り扱う書類やファイルについて、誰が見ても内容が容易に理解できるよう、周囲への配慮が行き届いた資料作成を行っていきたい。そうした日々の丁寧な仕事の積み重ねが、結果としてキャリアを切り拓くことにつながっていくと感じる。